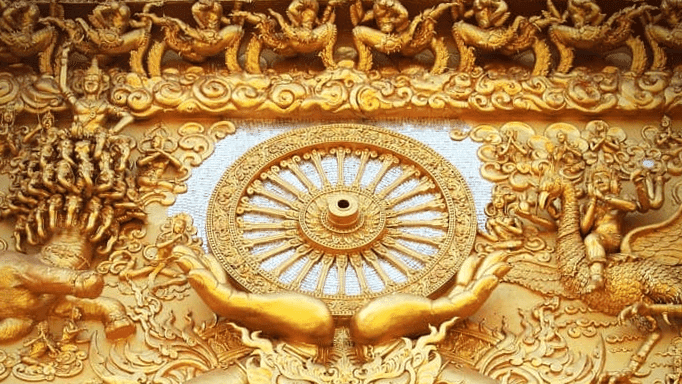右リング/左リングという二分法は、レーニン二分法のプロセス/結果またはエボリューション/ インボリューションと呼ばれることがよくあります。
「右」はプロセス、エボリューションに対応します。そして「左」は結果、インボリューションに対応します
社会的進歩の2つのベクトル
社会的進歩の2つのベクトルとしてのエボリューションとインボリューション
ソシオニクスの開発者であるAushra Augustinavichiute(オーシュラ・オーガスタ)は、社会の集合的な心の働きの本質として、社会的進歩という概念を導入しました。彼女は「ソシオニクスの全16タイプは、どのタイプも社会的要求の一部を担っている。すなわち、ひとつひとつのタイプそれぞれが、知的社会的機能そのものである」と考えました。
「要求関係、監督関係から成る4つの恩恵リングは、ソシオニクスの全16タイプそれぞれのニーズと懸念を社会的要求のシステムに変換するための、シンプルで信頼性の高いシステムです。恩恵リングとは、新しいアイデアの出現と、そのアイデアの実現化の過程に関わる社会を進歩させるエンジンのようなものです」(A.A.「タイプ間関係理論」より)。
4種類の恩恵リング:
要求関係における要求者(要求する側)→被要求者(要求される側)
右リング(別名:プロセス、エボリューション)
ILE → EIE → SEE → LSE → ILE(アルファ → ベータ → ガンマ → デルタ → アルファ)
SEI → LSI → ILI → EII → SEI(アルファ → ベータ → ガンマ → デルタ → アルファ)
左リング(結果、インボリューション)
LII → SLI → ESI → IEI → LII(アルファ → デルタ → ガンマ → ベータ → アルファ)
ESE → IEE → LIE → SLE → ESE(アルファ → デルタ → ガンマ → ベータ → アルファ)
4種類の改訂リング:
監督関係における監督者(監督する側)→被監督者(監督される側)
右リング(別名:プロセス、エボリューション)
ILE → LSI → SEE → EII → ILE(アルファ → ベータ → ガンマ → デルタ → アルファ)
SEI → EIE → ILI → LSE → SEI(アルファ → ベータ → ガンマ → デルタ → アルファ)
左リング(結果、インボリューション)
ESE → SLI → LIE → IEI → ESE(アルファ → デルタ → ガンマ → ベータ → アルファ)
LII → IEE → ESI → SLE → LII(アルファ → デルタ → ガンマ → ベータ → アルファ)
ソシオニクスには「クアドラ」という小グループがあります。
例えばILEはアルファ・クアドラです。上記のタイプをクアドラに置き換えると、恩恵リング、改訂リングいずれも、右リング側は「アルファ → ベータ → ガンマ → デルタ → アルファ」の順で遷移しており、その逆に左リング側は「アルファ → デルタ → ガンマ → ベータ → アルファ」の順で遷移しています。
社会的進歩リングとは、恩恵リング(要求関係からなるリング)と改訂リング(監督関係からなるリング)の両方で共通してみられるクアドラの繋がり(リング)を意味しています。
◆◆◆
ソシオニクスの16タイプは、二分法「右(プロセス・エボリューション) / 左(結果・インボリューション)」のいずれかに振り分けられます。
双対ペアは、かならず同じ二分法になります(例えばILEとSEIは双対ペアですが、Fig.1だとどちらも右側の青背景の部分に存在しており、いずれも「右(プロセス・エボリューション)」です。そしてこれが全ての双対ペアに言えます)。
右(エボリューション)リングは、アルファクアドラ(Fig.1 青背景)⇒ ベータクアドラ(Fig.1 赤背景) ⇒ ガンマクアドラ(Fig.1 緑背景) ⇒ デルタクアドラ(Fig.1 黄背景)方向に、要求する者⇒要求される者が連なっています。つまりエボリューションタイプにおける社会の進歩は、アルファ⇒ベータ⇒ガンマ⇒デルタの順で遷移するといえます。右リングは、社会の主流的な方向性を作り出しています。
左(インボリューション)リングは、全く逆向きの流れになります。こちらはFig.1の通り、インボリューションタイプにおける社会の進歩は、アルファ⇒デルタ⇒ガンマ⇒ベータの順で遷移します。左リングは、主流である右リングのプロセスを修正し、右リングとは異なる形で社会成長の貢献に寄与することができる、一種の「変種・バリエーション」を生み出すという役割を担っています。
◆◆◆
エボリューションとインボリューションという2つのプロセスから、社会の進歩(社会的進歩)の2種類の方向性を理解するというアプローチを提唱したのはV.V.Gulenkoです(V.V.Gulenko著「経年変化と再生の波について:ユングの特徴と組み合わせた進歩の方向性(1996年1月7日、キーウ)」)。
彼は、エボリューションとインボリューションの概念を、以下のいくつかの方法で検証しています。
「エボリューションは個体発生、つまり既存のキャパシティの展開です。インボリューションとはエピジェネシスであり、新しい形態や構造の出現、エネルギーの蓄積と貯蔵を経て、新しい生命の急速な爆発へと至るものです。
エボリューションは直線に展開する発展であり、水平方向の軌跡を定義します。一方インボリューションは、この直線的な発展をスパイラルに変化させるものです。水平方向へと進んでいた発展の方向性を垂直方向に向け、新しいフロンティアに向かう軌跡を刻みます。
エボリューション的な発展は、滑らかで均一です。インボリューション的な発展は断続的で不規則です」
エボリューションとインボリューションは、ダーウィンの自然淘汰の法則の2つの側面を反映しています。
「突然変異の出現は、インボリューション、つまり『左』の優位性に他ならないものです。そして適応の過程における選択または強化は、エボリューション、すなわち『右』の優位性に対応しています。
左のタイプは恒常性を乱し、それを回復させるのは右のタイプの役割です。どちらかの方向性に完全に振れると、特定の死に繋がります。この時の死の形には様々な形があります。
「右」によってもたらされる死は、徐々に冷えていき、衰退し、老化した結果として訪れるものです。「左」によってもたらされる死のスピードは速いです。「左」の死はオーバーヒート、爆発的に増え過ぎた生命の過飽和、若さの過剰から生じます」
「エボリューション、または循環的な進行は、ネガティブフィードバックに対応し、インボリューションはポジティブフィードバックに対応します。
インボリューションは不安定な指数関数的成長をもたらします。エボリューションは、生命に不可欠なパラメーターを安定化させることに繋がります。
「右(エボリューション)」的な進歩は、保存性と再現性を意味します。時間が経つにつれて、徐々に色あせていくのは、このような発達が老化、つまり徐々に劣化していくことを表しているからです。エネルギーは失われますが、より多くの情報が蓄積されていきます。
インボリューションは(中略)鋭い衝撃、すなわち急激な変化、急激な相転移として発生します。つまり、古いものから新しいものへの移動、若返り、活性化です。(中略)インボリューションは、縮んだコイルのように、急激な力に必要なエネルギーを凝縮しています。このエネルギーの蓄積は、システムの情報リソースの損失に比例します」
◆◆◆
したがって、上記の記述を要約・補足すると、2つの発展の方向性は次のようになります。
エボリューションによる発展は徐々に起こります。このエボリューションの特徴は、社会システムの複雑さの増大、人と天然資源の持つエネルギーの情報への変換、および文明の繁栄の中での具体化を特徴としています。
インボリューションは不規則かつ急速に進行します。インボリューションは、突然変異、飛躍、社会システムの単純化と再編成、社会的情報の圧縮、社会的エネルギーの放出を特徴としています。インボリューションは、人工的な文明から自然環境へと向かう逆方向の動きです。
◆◆◆
幼少期から青年期を経るエボリューション的進歩は、情報が溢れる高度に発達した社会へと導きます。
この運動は、エネルギーを浪費する暴力的な段階を経て、最終的には情報と文化の過剰の中でゆっくりと衰退していくことになります。
肥大化した人間のエボリューション的発達の果てに、巨大な脳を持ちながら萎縮した身体を持ち、完全に人工的に加工・改造された環境の中で生きる「ホモ・コンピュータ」が出現します。このような人が行わなければならない情報処理は、その複雑すぎる生活をコントロールするために非常に複雑なものになるため、その管理に多大な時間とエネルギーを費やすことになります。
インボリューション的な道は、老年から若年へ、死から再生へと反対の方向に進みます。
これは、若返り、再生、社会の情報の剥ぎ取り、社会のエネルギーの放出の道であり、情報過多のあまり過負荷を強いられている社会から「エネルギーに満ち溢れた社会」へと変化する道です。
インボリューションは生活の簡素化に繋がります。そして生命エネルギーは過剰になり、自然環境との調和が回復します。それが極端に進むと、インボリューションは文明社会を「原始的な昔の形態」へと戻します。
社会のエボリューション的発展は、社会システムの成長、進歩、複雑化の増大を確実なものにする必要がある初期段階において特に重要なものです。
社会のインボリューション的発展は修正的なものであり、老朽化した社会に、生産性のピークの時代を取り戻すものです。特に、社会を改革し、山積した問題を解消し、複雑に絡み合った非効率なシステムを再び扱いやすくするために、つまり社会の早期老化を防ぐために、という意味でインボリューションは重要な価値を持ちます。
◆◆◆
社会システムと個人が、情報とエネルギーのバランスのとれた状態で存在している状態を「最適」と呼ぶことにします。この状態は、青年期から成熟期への移行期に相当します。そして生命力のピークと社会的生産性の融合を表現しています。
2002年のカンファレンスにて、V.V.Gulenkoは、社会の進歩におけるクアドラの進行において、ベータ・クアドラとガンマ・クアドラが、権力をめぐって交互に入れ替わりながら、長期にわたって主導権争いしていることに気付くことができると述べています。この現象は、最適な段階を延長することを目的とした社会の自己修正メカニズムを反映しています。
この段階では、成熟期であるガンマ・クアドラから、青年期であるベータ・クアドラへの定期的な復帰があります。これはインボリューションのプロセスです。
このように、社会が最適な状態に維持されるためには、エボリューションとインボリューションのプロセスを交互に繰り返される必要があります。エボリューションは社会を進歩の道へと導き、インボリューションは社会の早すぎる老化を防ぎます。
ここで重要なのは、この主導権争い、あるいはエボリューションとインボリューションのプロセスにおいて支配的なのはエボリューション方向(エネルギーを情報に変換する方向)の流れだという点です。
最終的にはインボリューション側の力ではなく、エボリューション側の力の方が勝利します(エネルギーのエントロピーの法則にしたがいます)。
その後、社会の中心的存在である二つのクアドラ(ベータとガンマ:二分法「中心性(果敢)」)が相争い、脈動する時代は過ぎ去り、デルタ・クアドラの時代に突入します。
デルタ・クアドラの時代は、まるで完全な遺物のような状態のまま、非常に長い間続くことになります。これは、長い時間をかけて社会に十分なエネルギーが蓄積され、新しいアルファ・クアドラの時代、つまり新しいライフサイクルが始まるまで続きます。
左右のタイプの違い
エボリューション(右)とインボリューション(左)のタイプは、思考や行動のスタイルを決定する重要な要素です。
ここでは、エボリューションタイプとインボリューションタイプの違いを、身体的、心理的、知的、社会的の4つのレベルで考えてみましょう。
身体的レベル
活動の方向付けと、エボリューション(別名:右、プロセス)/インボリューション(別名:左、結果):
- エボリューションタイプ:プロセスの調整と微調整を得意としてます。その仕事ぶりは几帳面です。彼らはすべての詳細を考慮に入れて、材料を注意深く処理します。このタイプに特徴的な傾向として、活動のスムーズさ、活動の一貫性が見られます。
- インボリューションタイプ:一応は機能するものの完全ではないプロセスに基づいて、結果を生成する可能性があります。 大きな部分から始めて、小さな部分は後回しにします。このタイプに特徴的な傾向として、活動を鋭く、オンオフ的に切り替える点が見られます。新しい職業へ転職する傾向もみられます。
心理的レベル
内面世界の特徴:
(エボリューションタイプに比べると)インボリューションタイプは内面がシンプルに整理されています。内面の葛藤が少なく、より統合され、調和がとれています。しかし、そのような心理的な「電荷」の分布は、彼らの環境が持つ正反対の性質によって釣り合いを合わされています。
インボリューションタイプを取り巻く環境は、複雑かつ曖昧であることがほとんどです。彼らの生活環境は不安定で、予測不可能なことが多いのです。常に紛争地帯に住み、優先順位が頻繁に変わりますが、これがインボリューションタイプを妨げることはほとんどなく、それどころか、そうした環境こそが彼らの好む環境なのです。
一方、(インボリューションタイプに比べると)エボリューションタイプは内面的には複雑かつ曖昧です。環境的には、シンプルで曖昧さのない環境、突然の変化を防ぐことが出来る環境でのみ存在できます。
◆◆◆
私の考えでは、インボリューションタイプとエボリューションタイプの心理は、意識と無意識に関して、発達の度合いや方向性が異なるのだと思います。
エボリューションタイプは、意識の枠組みがより発達し、精神的プロセス、思考、行動がより複雑で、社会儀式的な行動もより複雑なものです。
エボリューションタイプは自分の評判の維持に焦点を合わせています。そしてそれは、現代社会の複雑なヒエラルキーにおける彼らの重要性を増すことになります。
しかしエボリューションタイプは、内的には、より無意識と葛藤します。そして彼らはその葛藤を、他の多くのエボリューションタイプの人々を巻き込んだり、心理的に近い距離にいるエボリューションタイプ同士の関係性を悪化させるような、様々な精神・社会的な過剰という形で解消しようとします。
インボリューションタイプは、シンプルで自然な意識の枠組みを持っています。彼らはエボリューションタイプよりも無意識との調和がとれています。
インボリューションタイプの行動や思考は、よりシンプルで自然なものです。そのため一般的にインボリューションタイプは調和的で内面が充実しており、大衆運動や過剰への参加を回避する傾向があります。
しかし、この意識的な枠組みにおけるシンプルさゆえに、インボリューションタイプには現代社会の複雑な生活や、仕事や公共の場での凝った集団儀式には適応しにくいという面もあります。
そのためインボリューションタイプは少人数のグループで協調的に作業するほうが向いていると言えます。
知的レベル
インボリューションタイプは一般的なものから始まり、詳細へと進みます。
エボリューションタイプは詳細から始まり、一般的なものへと進みます。
形式論理学では、この2つの情報経路を演繹と帰納と呼んでいます。このような考え方の違いは、本を読む、論文を書く、人前で話すといった活動にも目に見える形で影響を及ぼします。
インボリューションタイプは、本を読むときに、まず全体像や最終的な結論を確認し、そこに著者がどのように到達したかを追跡することから始める傾向があります。
また、インボリューションタイプの人は、自分の考えを述べる際に、まず一般的な原理とその結果のパターンを述べ、その後に詳細な説明と具体例を挙げるというやり方を好む傾向もあります。
それに対し、エボリューションタイプは全く逆の方法で情報を認識して提示する傾向があります。
彼らは先にジャンプせずに、最初から順に本を読むほうが快適に感じる傾向があります。
エボリューションタイプが行動する際には、まず詳細、出発点、手持ちの証拠を提供し、最後になってから初めて最終的な結論を提示します。
エボリューションタイプ:情報を複雑化する傾向があります。彼らはより複雑で詳細に考えるため、思考プロセスが遅く、エネルギーをより消費します。しかし彼らの知的成果物は、意図した方向によく考え抜かれたものになります。
エボリューションタイプの思考の強みは、人工的な洗練と徹底にあります。
欠点は、処理速度が遅く、結果が出るのが遅いという点です。
また、特定の案件の詳細を研究しているうちに、広い視野を見失うことがあります(これは「トンネルビジョン」と呼ばれます)。
膨大で複雑な文章や作品は、精神的な進歩の原動力であるエボリューションタイプの精神の集中的な仕事の結果だと言えます。彼らはこのプロセスに多大な労力を費やして、素晴らしい結果を生み出しているのです。
インボリューションタイプ:情報を単純化する傾向があります。彼らの思考は素早く、洗練する余地が残っている未加工の成果物を提供します。
インボリューションタイプの思考の強みは、自然なシンプルさ、問題の一般化された全体像の迅速な提供、および、結果の迅速な提供にあります。
インボリューションタイプの欠点は、情報を簡潔に表現しすぎること、そして重要な可能性のある詳細に注意が払われていないことです。
インボリューションタイプの中でも特に優れた人の生み出す考えは、見事なまでのシンプルさ、完全性、明快さを備えています。情報を集約し、状況を理解し、コントロールするための主要な側面を把握し、シンプルな方法で迅速に結果を出します。
社会的レベル
自然 - 人工(文明)
インボシューションとエボリューションの違いは、「自然 - 人工(文明)」として簡単に説明することができます。
自然は文明化されていません。そこには国家が尊重する伝統、法律、哲学、宗教は含まれません。ここでいう「文明」とは「自然ではないもの」です。
一方、人工的社会(文明社会)が公言する道徳は、本質的に「生存競争という自然法則」からは導き出せないものです。
インボリューションタイプは自然な存在の生き方やモデルに近いです。
エボリューションタイプは人工的(文明的)な社会に近いと言えます。
◆◆◆
グループでの作業:
インボリューションタイプは自分のテリトリーの外の環境では消極的なコミュニケーションしかとらないため、大きな集団になるのが難しいです。見知らぬ人に対する消極的な態度は、より大きな集団を形成することを阻害します。また、非公式なコミュニケーションをとる余地がある少人数のグループで仕事をする傾向があります。
それに対して、エボリューションタイプは組織化された大きな集団の中でうまく機能します。しかし、少人数のグループで作業する場合、コミュニケーションの距離を縮めるとエボリューションタイプは不寛容になる傾向があるため難しいです。
つまり、下記のことが言えます。
- エボリューションタイプ:小グループ内の困難な近距離コミュニケーションや、そこで起こる頻繁な不協和音や競争によるマイナスを相殺できるような、自分が所属する部門以外の社員と良好な関係を築ける大組織での仕事を好みます。
- インボリューションタイプ:仕事やコミュニケーションが厳しく規制されず、労働時間が柔軟で自己表現の自由度が高い、小グループでの協調的な仕事に引きつけられる傾向があります。
エボリューションタイプとインボリューションタイプの根本的な心理や認知スタイルの違いは、しばしば誤解や対立を引き起こし、それが複雑な大組織や最高レベルの公的管理からインボリューションタイプを追い出す傾向を生み出します。
筆者の考えでは、インボリューションタイプは、物事をもっとシンプルにしたり再編成する必要性が生じた時、過度に精巧なプロセスが組織や社会の効率を犠牲にし始めた時にのみ、そのようなポジションに着任するのだと思います。
エボリューション/インボリューションの区別と社会構造内での特徴
エボリューション(右)による社会の進歩は、マクロレベルの動き、つまり「大きな組織レベルでの社会の動き」を反映しています。
エボリューション(右)進歩は、スムーズな段階的発展を辿ります。そこでは、数多くの突然変異やイノベーションの中から、社会全体への大量複製に最も適したものを選択されることになります。多くの場合、最も顕著なものをマークし、それを政治的に強化し、一貫して実装に導くことになります。
エボリューション(右)という社会的進歩は、アルファ⇒ベータ⇒ガンマ⇒デルタという方向性で進行する周期的な動きから生じるものです。
インボリューション(左)による社会の進歩は、ミクロレベルの動きを反映しています。これは、アルファ⇒デルタ⇒ガンマ⇒ベータという逆方向の動きです。
インボリューション的発展には、エボリューション的発展を修正する作用があります。しかし、インボリューション方向への流れが強くなりすぎると、エネルギーが過剰に蓄えられてしまい、社会に損害が生じる危険性があります。
これに対抗するために、社会はエボリューションという強力な安定化メカニズムを備えているのです。
◆◆◆
社会では、エボリューションのベクトルが支配的なものです。 これはソシオニクスの観点から、次のように説明できます。
まず第一に、前述したようなエボリューションタイプとインボリューションタイプの違いから説明可能です。
エボリューションタイプは大人数での仕事を好み、インボリューションタイプは少人数での作業を好みます。エボリューションタイプは社会的儀式における思考と行動の複雑さを志向するため、インボリューションタイプと比較してマクロレベルの社会運営の、かなり複雑なプロセスのマネジメントに適性があります。
第二に、中心性クアドラであるベータ・ガンマと、周辺性クアドラであるアルファ・デルタのうち、「社会の中心を支配しているのは前者のベータ・ガンマのほうである」というV.V.Gulenkoの経験則に対する、筆者らの観察結果から説明可能です。
筆者らも、上記のV.V.Gulenkoの経験則が、かなり一般的に観察できることを確認しています。しかしそれと同時に、「社会の支配」という観点から言えば、中心性/周辺性(ベータ・ガンマ/アルファ・デルタ)以上にエボリューション(右)/インボリューション(左)の与えるインパクトのほうが相当に大きいことを観察しました。
エボリューションタイプの優位性は、その数の優位性と組織の複雑さだけで説明することはできません。
ところで、V.V.Gulenkoは上記の経験則とは別に、中心性クアドラ(ベータとガンマ)同士の競争をした際に、社会から押し出されてしまいやすいタイプの存在についての考えも提唱しています。
IEI(ベータ、インボリューション、内向)は戦闘的なベータクアドラの中で平和を作り出し、調和をはかるタイプであり、ベータクアドラ同士の競争をすると、社会の隅に押し出されてしまうタイプだとV.V.Gulenkoは言及しています。
ガンマクアドラではESI(ガンマ、インボリューション、内向)がこれに相当します。ESIは道徳的な異議申し立てをすることで、ガンマクアドラの他のタイプ( SEE, ILI, LIE )が持つ実利主義的な攻撃性を抑制します。
このように、エボリューションタイプの中でも非常に社会の中心的なタイプとして、下記の4タイプをあげることができます。
- EIE(ベータ、エボリューション、外向)
- LSI(ベータ、エボリューション、内向)
- SEE(ガンマ、エボリューション、外向)
- ILI(ガンマ、エボリューション、内向)
ベータ、ガンマの残りの4タイプのうち、SLE(ベータ、インボリューション、外向)とLIE(ガンマ、インボリューション、外向)は、インボリューションではありますが、外向タイプでもあり、それゆえか中心性クアドラらしい戦闘性を持っています。
しかし、中心性クアドラ(ベータ・ガンマ)でも、インボリューションかつ内向であるタイプ、すなわち下記の2タイプは、IEIとESIは、いずれも社会の中心から押し出されてしまうことになります。
- IEI(ベータ、インボリューション、内向)
- ESI(ガンマ、インボリューション、内向)
このように、エボリューションタイプが優位になる傾向は、他の著者も指摘しています。
A.V.Boukalovは、グロフの周産期マトリックスとタイプの世界観の関係についての研究(「個性の形成過程における情報代謝の機能形成メカニズムについて」)の中で、社会における政治闘争について論じていますが、彼はしばしば政治舞台はEIEとLSIという二つのタイプによって占められ、その闘いは最終的にLSIの勝利で終わると書き記しています。
本質的には(そしてこれは社会政治的価値の世界的な問題ですが)、どういう人が高い地位に就くのに適しているのかという問題があります。
たとえ「本人のため」であっても、個人に対して制限や強制を加えるという点では、行政システムや強制収容所といったものが、「典型的にベータクアドラ的」であることに疑いの余地はありません。
重要なのは、ベータクアドラの競合する代表者から構成されるグループの中で勝利する双対ペアはLSI-EIEであり、SLE-IEIは、LSI-EIEによって排除されるということです。
さらに、このLSI-EIEという双対ペアの中での勝者はLSIです(LSIは最も独裁的な傾向の強いタイプです)。このような統制をとるタイプとしてはLIIも挙げることが出来ますが、LIIはLSIとは別の形の統制をとります。
これはまさに現代ウクライナの政治情勢でも起こっていることです [3]。
社会的な危機的段階を脱した途端に、YanukovychやPoroshenko(ともにSLE)といったインボリューションタイプの政治的指導者が徐々に中心的なポジションを追われ、代わりにViktor Yushchenko(LSI)とYulia Tymoshenko(EIE)が政治的指導者になったのです。
これは【インボリューションタイプが小グループでの活動を志向し、思考や行動が単純で、政治生活の複雑さを深く掘り下げて適切に対応しようとせず、歴史の中の静かな時期における社会発展の複雑なプロセスを効果的に管理できないこと】が主な原因で生じたことだと私は考えています。
しかし危機の時や、過度に複雑で効果のないプロセスを改革する必要がある時、あるいは戦争の時、危険に直面した時に、インボリューションタイプは社会の頂点に呼び出されるのです。
これがVladimir Gulenkoが運動エネルギーグループ理論(theory of ekfinal groups)にて、中心性クアドラのインボリューションタイプ( SLE, IEI, LIE, ESI )のことを改革(reform)のグループと呼び、中心性のエボリューションタイプ( EIE, LSI, SEE, ILI )のことを社会プロセスの修復(repair)のグループと呼んだ理由です。
要求関係と監督関係の社会的・心理的意味
ソシオニクスの最初の開発者であるAushra Augustinavichiuteは、「ソシオン」、すなわち「ソシオニクスの全16タイプと、それらの間の関係の総和からなる社会集団、あるいは社会的知性の集合的精神」の本質を理解するための重要な鍵として、「社会的進歩(social progress)」という概念を紹介しました。ソシオニクスはまた、Aushraによれば、社会構造やタイプ間の関係を調べることを目的にした社会科学の新しい分野である「ソシオマティカ(sotsiomatika)」を生み出します。
Aushraによれば、「あらゆる種類、あらゆるタイプの知性それぞれが、社会的要求の一部分を担い合い、各々が社会的機能のひとつとして働いている」のだと考えられています。
この社会的進歩は、要求関係による、要求者から被要求者への推進力伝達(平たく言うと「勢い」の伝達)と、監督関係による、社会的要求の履行の管理に関連しているとAushraは説明しています。
被要求者は要求者の推進力を察知し、要求者が策定した問題を解決しようと努力します。監督者は、被監督者と要求者の接近を妨げ、(被監督者に要求者からの要求ではなく)社会からの要求を実現させます。
◆◆◆
Aushraは、要求関係を催眠の神秘的な関係、監督関係を心理的抑圧の恐ろしい関係と表現しています。
V.V.Gulenkoは、要求関係と監督関係の本質を別の形で定義しています。
彼は、要求関係の恩恵リングは「エネルギー・パルスの伝達、エネルギーの取り込み」であり、監督関係の改訂リングは「情報の伝達・仕事からのシャットダウン・監督者による被監督者の行動の修正」であると説明しています [4]。
◆◆◆
要求関係の本質的な社会的価値は、下記の通りです。これによって、クアドラの進行が可能になります。
- 要求者が、被要求者のエネルギーを活性化させ、強制的に、被要求者を「社会的に意味のある活動」に参加させること。
- 被要求者の情報を、要求者が模倣すること。
そして、監督関係の本質的な社会的価値は、下記の通りです。こ
- 監督者が被監督者に働きかけ、被要求者に(要求者タイプからの要求ではなく)社会的な要求(社会から求められていること)を履行させつつ、被要求者の不適切な行動を抑制すること。
- 監督者が、「被監督者ではなかなか解決できない難問の解決支援」をすること。
筆者自身は、情報の取引とエネルギーの取引の両方が考慮されるべきであると考えています。
◆◆◆
要求関係には、どのような取引があるのでしょうか。まず要求者→被要求者の流れを見てみたいと思います(Fig.2)。
- 要求者の第2機能 → 被要求者の第5機能:
第2機能は「創造機能」、第5機能は「暗示機能」とも呼ばれます。ここでは、① 要求者から被要求者へのエネルギー伝達、② 要求者による被要求者の活動の一方的で無意識的なプログラミング、③ 要求者の活動への巻き込み(要求者が巻き込む側、被要求者が巻き込まれる側)が生じます。①②③によって要求者は、被要求者に対して「創造的、暗示的」な影響を与えます。(Fig.2 左図)。 - 要求者の第1機能 → 被要求者の第8機能:
要求者が「刺激 - 反応」の原理に従って動く行動主義的エネルギー・レバーを作動することで、被要求者のバイタルリング(第5,6,7,8機能)の動作がアクティブになります(Fig.2 右図)。ちなみに、要求関係では一方的に要求者が被要求者のレバーを操作していますが(つまり要求者→被要求者への一方的なエネルギーの伝達しかありませんが)、疑似同一関係では、相互にレバーを操作し合い、相互にエネルギー伝達しあっています。
次に、被要求者→要求者の流れを見てみたいと思います(Fig.3)。
- 被要求者の第7機能 → 要求者の第4機能:
第4機能は「脆弱機能」とも呼ばれます。これによって、被要求者は、要求者の苦手とする機能に、「シンプルで適切な行動プログラムの情報」を与えます(Fig.3 左図)。 - 被要求者の第2機能 → 要求者の第7機能:
この流れによって、被要求者が、要求者の第7機能の狭い基準を拡張、拡大します。被要求者から要求者へと「創造的な行動方法に関する情報」が伝達されます。(Fig.3 中央図)。 - 被要求者の第1機能 → 要求者の第6機能:
第6機能は別名「動員機能」と呼ばれる機能です。ここでは、まず要求者が「被要求者のアビリティ」を模倣しようとします(つまり被要求者 → 要求者方向に情報伝達が生じます)。被要求者の第6機能は、要求者の模倣に伴って活性化されることになります。(Fig.3 右図)。
Fig.2、Fig.3をまとめると、エネルギーは要求者から被要求者へと移動するのに対して、情報は逆方向(被要求者→要求者)へ移動していることがわかります。
◆◆◆
監督関係には、どのような取引があるのでしょうか。まず監督者→被監督者の流れを見てみたいと思います(Fig.2)。
- 監督者の第1機能 → 被監督者の第4機能:
監督者の強力な第1機能が、被監督者の脆弱な第4機能に情報を伝達します。これは、監督者の視点から見た場合、「被監督者の不適切な行動の修正とサポート」という意味合いを持ちます。一方、被監督者の視点から見た場合、これはエネルギーのスイッチを切る流れであり、意欲を失わせる流れでもあります。人は一般的に、第4機能が刺激されると、痛みやフラストレーションを感じますが、それがこの場合にも起こるからです。 - 監督者の第2機能 → 被監督者の第1機能:
監督者の第1機能→被監督者の第4機能へと情報が流れる際、同時に第2機能→第1機能へも情報が流れます。第1機能→第4機能と、第2機能→第1機能の2種類の情報の流れによって、メンタルリング(第1,2,3,4機能)に沿った情報の移動が可能になります。
- 被監督者の第8機能 → 監督者の第5機能:
第5機能も第8機能も、どちらもバイタルリング(第5,6,7,8機能)に含まれる機能であり、無意識的な機能です。被監督者は、自分でも意識しないうちに、監督者の第5機能(外部からのサポートを強く求めている機能)に影響を及ぼし、監督者のエネルギーを満たします。 - 被監督者の第7機能 → 監督者の第8機能:
被監督者の第7機能が、監督者の第8機能に対して受け入れられるプログラムを提供します [5]。
◆◆◆
要求関係と監督関係の情報・エネルギー伝達の説明から、次のことがわかります。
- 恩恵リング(要求関係から形成されるリング)の場合、エネルギーは要求者→被要求者へと流れます。そして情報は被要求者→要求者へと流れます。
- 改訂リング(監督関係から形成されるリング)の場合、エネルギーは被監督者→監督者へと流れます。そして情報は監督者→被監督者へと流れます。つまり恩恵リングとは真逆です。
このように、では、エネルギーは被要求者から要求者へと移動して一方的な活性化の連鎖を形成しますが、監督関係では、エネルギーは被監督者から監督者へと移動します。そうしてエネルギーを得た監督者は、被監督者が抱えきれなくなったフラグをキャッチし、一方的な保護の連鎖を形成します。
それと同時に、情報がエネルギーとは逆方向に動いています。
情報は被要求者から要求者に移動します。一般的に考えられることが多い「要求者→被要求者の流れ」とは逆の流れなので、この現象を「逆要求」と呼びます(Gulenkoの用語です)。
「逆要求」の主要な社会的特性は「模倣」です。これによって社会や組織の中で、あるクアドラの価値が次のクアドラに転送されます。
例えば、要求者EIE(ベータ)は被要求者SEE(ガンマ)を模倣した結果、EIE本来のイデオロギー的な偏向を失い、自由と繁栄の価値観に浸るようになります。また、要求者LSI(ベータ)は被要求者ILI(ガンマ)を模倣した結果、より慎重で懐疑的、実用主義的になります。
◆◆◆
逆要求の情報の取引で肝要なのは、第2機能から第7機能への転送です。
- 被要求者の第2機能 → 要求者の第7機能:
第2機能は「創造機能」であり、第7機能は「無視機能(別名:監視機能)」と呼ばれます。ここでは、被要求者は、要求者に新しいタイプの行動例を創造的に示します。第7機能は規範的な機能であり、他者の知識やノウハウを獲得し、価値観を調整する働きをする機能です。また、第7機能は、自分の双対タイプの思考を併せ持っています [6]。
◆◆◆
ここまでは、要求関係における情報の流れを説明しましたが、監督関係の場合、監督者から被監督者へと情報が流れます。
- 監督者の第1機能 → 被監督者の第4機能:
情報伝達の流れです。監督者から送信された情報は、監督者と共通の思考様式 [7]を持つ被監督者によって十分に受信され、さらに監督関係の連鎖の下流へと情報が伝達されていきます(SEI→EIEへと伝達された情報が、EIE→ILIへと伝達されていきます)。 - 監督者の第2機能 → 被監督者の第1機能:
情報伝達の流れです。上記の「監督者の第1機能 → 被監督者の第4機能」と同様のことが起こります。
◆◆◆
一方的な援助が行われ、それが連鎖している場合、監督関係におけるエネルギー交換はスムーズに行われます。
ここで、監督関係間で生じている支援の方向性をトレースしようとした場合、「逆改訂」という概念も考えなければなりません(要求関係で「逆要求」というアイデアが登場したのと同様です)。
◆◆◆
これらのことから、情報の流れと言う面から見た場合、要求者のエネルギーサポートと監督者の情報修正によって、心理的に弱い側のタイプ方向(被要求者・被監督者方向)に向かって、新しいクアドラの価値の導入(情報の移動)が起こると言えます。つまり情報は「要求者→被要求者」「監督者→被監督者」方向へと受け渡されていくことになります。
あたかも心理的に強い側のタイプ(要求者、監督者)が「新しい目標や価値の松明」を心理的に弱い側のタイプに受け渡しているかのように見えるかもしれません。
それに対して、エネルギーの流れという面から見た場合、全く逆のことが起こります。つまりエネルギーは「被要求者→要求者」「被監督者→監督者」方向へと受け渡されていくのです。
これは解決不可能な問題に遭遇したとき、心理的に弱いクアドラ側のタイプが、心理的に強いクアドラ側のタイプに置き換わることを表しています。
なお、ここまでの話とは別に、社会的レベルではベータとガンマが支配的であり、アルファとデルタはしばしば補助的な役割を果たすことを考慮する必要があります。
社会的使命
ここでは、各タイプが社会の発展に果たす役割、すなわち「社会的使命」について見ていきたいと思います。
ソシオニクスの最初の開発者であるA. Avgustinavichueteによれば「全ての情報代謝タイプは、それぞれ特定の社会的機能を実行する」とされています。
インボリューションタイプは、環境の課題に対してさまざまな解決策を生み出し、社会を飛躍的に前進させます。
エボリューションタイプは、最も価値のあるイノベーションをピックアップして社会に広め、社会システムを安定させます。
インボリューションタイプの社会的使命
- ESE(熱狂者) - 感情的な成長を提供し、人々に感情的なエネルギーを与え、革新的なアイデアと社会的実践を広めます。
- LII(分析者) - 基礎科学の触媒、システムの革新者・再編成者。多くの代替案を生み出し、人が目指すべき未来の理論的モデルを構築します。「論理的な」成長の起点になるような人で、人に考えることを促します。
- SLE(元帥) - 実用的で革命的。自らの敵を打ち破り、古いシステムを破壊し、新しい構造を作り出す者。歴史を貫く力。
- IEI(叙情詩人) - 明るい理想の未来、人の魂を照らす夢の創造者。
- LIE(起業家) - 革新者。ビジネス界のイノベーター、応用科学における実験者、新しい方法、戦術、経験的な情報を発見する。
- ESI(守護者) - 悪に立ち向かい、断固として道徳的な基準を守り、新しく成功したイノベーターのための倫理と道徳的な基盤を作る。
- IEE(助言者) - 人の能力や可能性を発見し、困難な状況から抜け出す道と信頼できる有能な人材を見つけ出し、人道的なアイデアを生み出す。
- SLI(職人) - 最小限の資源と労力で、飛躍的に効率性を高め、迅速に結果を出せるシンプルな技術や仕事の手法を創造する。
エボリューションタイプの社会的使命
- ILE(探求者)- 有望な発見やアイデアを見つけ、それらの形成と安定化に貢献し、それらの性質を解明すること。そういった発見やアイデアを基礎にして正確な公式と理論を導き出し、自らそれに従いながら、社会への普及を促進すること。
- SEI(仲介者)- 美的で落ち着いた快適な環境を作ることで、過度な競争や苦しい労働の雰囲気を和らげ、楽しく交流できる雰囲気を作り出すこと。
- EIE(指導者)- 社会の不満を認識し、思想的(イデオロギー的)な指導者として戦闘集団に参加し、その集団の思想をより大きな集団に広めること。闘争に全エネルギーを注ぎ込み、それを使い果たすこと。
- LSI (検査官)- SLEの改革的な行動を結論づけ、社会全体に新しい構造を広め、安定させ、規制し、規律と秩序を確立し、権力の階層を強化すること。
- SEE(政治家)- 強い影響力を持つ階級や、経済志向の傾向の強いグループの代弁者。政治的な駆け引きをリードし、政治的、および外交的同盟関係を締結し、争い合う者同士を一時的な和平協定に導くことで、社会の政治的な状況を安定化させること。
- ILI(批評家)- 無謀で軽率な判断や行動を批判し、起こりうる危険や悪い影響を予測することを通して、社会の発展の方向を最も安全ではっきりした見通しの立てられるコースに絞り込むこと。
- LSE(管理者)- 誠実な無私の労働に基づいて、新しい経済関係の安定化の中で、工場型労働の生産性を向上させる特別な技術を取り入れ、それを社会に普及させるリーダーになること。
- EII(人文主義者)- グループの心理的風土を調和させ、良好な関係の芽をサポートし、競争の雰囲気を穏やかなものに変えること。進歩的なダイナミクスを推進するのではなく、それを犠牲にしてでも良好で安定した関係性を優先させること。
社会的行動のプロファイル
V.V. Gulenkoの「社会の進化について」(1991年、キーウ)にて、社会的行動のプロファイルが言及されています。
- インボリューション・内向型(SLI、LII、ESI、IEI):アーマラー(甲冑師・兵器製造者) - 社会の進歩のばねを締めるタイプ。進歩に必要なエネルギーを抽出し、突破に必要な物すべてを後続のグループに供給します。
- インボリューション・外向型(ESE、SLE、LIE、IEE):ファイター - 新しい可能性を見つけるという点において、最も活動的、精力的、かつ断固とした態度をとるタイプ。前のグループのアーマラーが集中させたエネルギーを、強力に爆発させる役割を果たします。
- エボリューション・外向型(ILE、EIE、LSE、SEE):サーフェーサー(塗装する人) - 社会のトップに誘われ、社会的進歩の前夜に訪れる激動の荒波を乗り切ります。彼ら自身はエネルギーを引き出すことも、運ぶこともしませんが、それを正しい方向へ導くことができます。サーフェーサーには、大衆の不満を言語化することを目指すイデオロギーの伝道師や、大衆、国家、社会の特定の層を代表して話すことができる技術によって地位を獲得した政治家が最もよく見受けられます。
- エボリューション・内向型(EII、ILI、LSI、SEI):エバキュエーター(排煙器) - 社会運動のエネルギーを散逸させ、将来のイベントのための領域を確保します。エバキュエーターの特徴は、感情の爆発を抑制し、重要な時期を円滑に進めようとすることです。
ビジネスにおける進歩の方向性
左チームと右チームの特徴
チームの特質は、多くの点で左(インボリューション)/右(エボリューション)によって決定されますが、これらを還元することは出来ません(非還元主義)。
インボリューションタイプと「左」組織の特徴
- インボリューション・動的
認知スタイル:ヴォーティカル・シナジェティクス
ESE, IEI, LIE, SLI - インボリューション・静的
認知スタイル:ホログラフィック・パノラマ
LII, SLE, ESI, IEE
この両タイプの思考は、単純さ、簡潔さ、および便宜性に引き寄せられます。行動や意思決定においても、インボリューションタイプは迅速に結果を得ることに重点を置いています。このタイプは、短期的な仕事を好み、活動の切り替えを頻繁に行い、場合によっては結果を改善するために戻ってくることもあります。急速な勢いでエネルギーや資源を消費し、それを再び蓄積するような、浮き沈みの激しい仕事ぶりが見受けられます。このタイプは、ムラのある活動を許容する風土があるビジネスに適しています。
インボリューションタイプは近距離 [8] で最も適応力があり、遠距離 [9] で仕事をすることを嫌うため、チームのすべてのメンバーと「ソフトな」関係を持つことを奨励する小グループや小さな組織で仕事をすることを好みます。このような集団では、余計な複雑さを排除したシンプルで効率的なスキームで仕事を進めることができます。彼らは、自分の活動や情報を単純化する傾向があります。インボリューションタイプで構成されるグループには、豊富なエネルギーを、グループプロジェクトのために自由に、潤沢に使用するという特徴があります。
活動の単純化と情報処理の速さにより、外部の変化に柔軟に対応することができます。このような単純さの欠点は、グループ構造や専門的な取引にある種の原始性があり、単純な方法、ツール、技術を好み、時には平凡な結果しか出せないことがある点です。
エボリューションタイプと「右」組織の特徴
この両タイプの思考は、複雑で徹底した細部へのこだわりにひきよせられます。その結果、結果を得るまでに多くの時間を必要とします。彼らの行動や判断は比較的淡々としており、状況の微妙な違いをすべて考慮した上で、プロセスに焦点を合わせます。エボリューションタイプで構成されたチームは、よりスムーズに、一貫性を持って均等に仕事をし、エネルギーとリソースを計画的に使い、作業の過負荷を避けることができます。
エボリューションタイプは、遠距離では順応性がある一方で、近距離ではそれほど順応性がありません。そのため、他のチームとの良好な評判や相対的な「ソフト」な関係が奨励され、その一方でチーム内では手厳しい関係が許される大きなグループや大組織で、最も効果的に働く傾向があると言えます。エボリューションタイプの大組織の特徴は、多層的な階層型の組織構造と業務手順を有し、多くの人々の努力を必要とする大規模な業務が存在し、集団的な仕事の成果を生み出していることが特徴です。
このような組織の欠点は、過度の形式化と官僚化のせいで、柔軟性に欠けているという点です。外部環境の変化への対応の遅れ、労働者の創造的エネルギーや表現の自由の抑圧があります。また、チーム内の競争関係が強まると、内部での闘争や陰謀が起こり、効率性や生産性が損なわれることもあります。
注意:本記事の出典は、ある程度ソシオニクスの知識がある人向けに書かれた記事であり、直訳しただけだと難解なため、大幅に意訳しています。本サイトの他のページは、基本的に注釈を注釈として分かる形で記載していますが、本記事は注釈がないと理解しにくい内容が非常に多いため、そのルールから逸脱して翻訳しています。「この用語の意味を理解していないと本文の内容の大半がわからなくなる用語の注釈」は、本文中に注釈なしに補足したり、日本で一般的な用語に置換したりして記載しています(例えばFig.1の直下に、「恩恵リングにはILE → EIE → SEE → LSE → ILEがある」といった原文にはない説明を追加したり、原文では「第1クアドラ」と書かれている用語を、日本で一般的な用語である「アルファ・クアドラ」や「アルファ」に置換しています)。また、本記事の図表は全て原文には存在しない物であり、訳者が原文をもとに独自に作成した物です。
訳注
- ^ 近距離:空間的な意味で密接に接触して行われるコミュニケーションで見られる距離。自発的に行われる点が特徴で、近距離(自宅、または外部からのコントロールを受けない身近な環境)ではリラックスして行動できる。最大8人までのグループに最もよく見られる。関連記事「モデルG」
- ^ 遠距離:人が外部から観察され、評価されるような社会の中で見られるコミュニケーション距離。遠距離のコミュニケーションは意識的に行われ、かつ社会的統制に大きく左右される。この距離は通常、見知らぬ人々の間または8人より多いグループで発生するとされている。関連記事「モデルG」
- ^ この出展が書かれたのは2005年なので、ここでいう現代ウクライナというのもその頃の時代をさしている。
- ^ V.V.Gulenkoは監督関係を情報代謝に、要求関係をエネルギー代謝に関連付けている。関連記事「モデルGの歴史とエネルギー代謝」
- ^ プログラムというとエネルギーの伝達と言うよりむしろ情報の伝達に見えるが、出典上では、被監督者→監督者の流れは「エネルギーの伝達」として説明されている。これは、要求関係側のエネルギー伝達の説明で登場した「要求者の第1機能 → 被要求者の第8機能」の部分に登場する、バイタルリングをアクティブにすることに相当するものとして出典の著者が解釈しているためではないかと思われる。
- ^ 双対関係の場合、片方のペアの第7機能と、片方のペアの第3機能が一致する。第3機能は「役割機能」とも呼ばれる機能である。一般的に人は、第3機能の情報要素について、「他人の期待に応え、社会で何かを成し遂げるために「努力」しなければならない個人の弱点だと認識している」とされる。
- ^ 認知スタイルのこと。監督者と被監督者は、必ず認知スタイルが同じである。タイプと認知スタイルの対応関係は下記の通り。
ILE, LSI, SEE, EII:因果的決定論的
SEI, EIE, ILI, LSE:弁証法的アルゴリズム的
LII, SLE, ESI, IEE:ホログラフィック・パノラマ的
ESE, IEI, LIE, SLI:ヴォーティカル・シナジェティクス的 - ^ 近距離:注釈 [1] 参照。
- ^ 遠距離:注釈 [2] 参照。