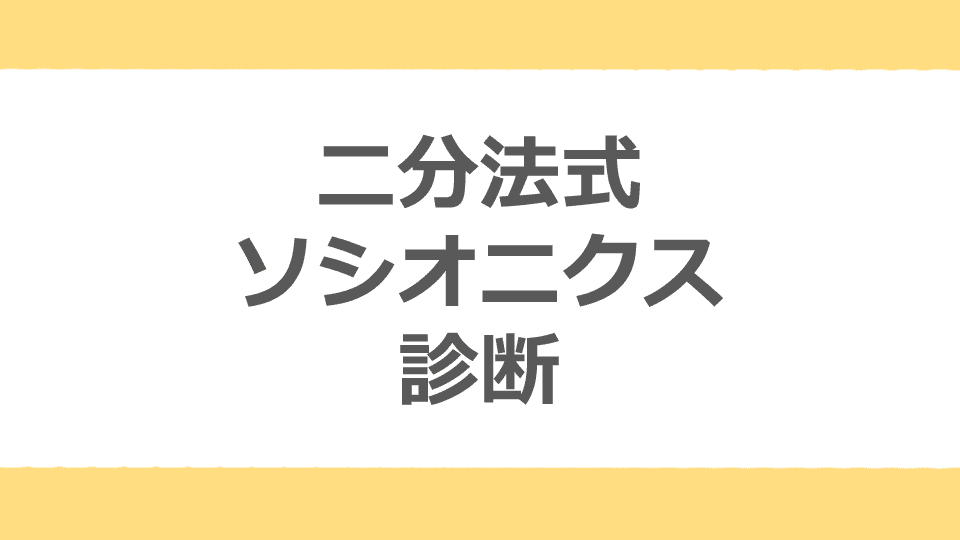診断テスト(全40問)
このテストでは、ソシオニクスのタイプ・サブタイプ・クアドラ、二分法・機能を測定します。精度は完璧ではありませんが、ソシオニクスに興味を持つきっかけになれば幸いです。
クアドラについて
- テスト結果に表示されるクアドラは、「あなたのタイプのクアドラ」ではなく、「回答傾向から見たクアドラ的な特徴」です。
- そのため、テスト結果のタイプと、理論上のクアドラと結果が一致しないことがあります。
~回答の仕方(タップで展開)~
- 直感で選ぶ
- AとB、どちらの特徴が「自分らしい」と感じるかを選んでください。
- 多い方にチェック
- Aの特徴に当てはまるものが多ければA、Bの特徴に当てはまるものが多ければBを選びます。
- 中間を選んでもOK
- どちらも同じくらい当てはまる場合や、AとBそれぞれの要素を持っていると感じる場合は、中間を選んでください。
- 例:「リーダーシップを取りたがる」と「人あたりがソフト」の両方が当てはまる場合や、「リーダーシップを取りたい時とそうでない時が半々」のような場合は、中間を選んで問題ありません。
ソシオニクスは、一般的な性格診断(ビッグファイブや公式MBTIの質問票の理論構造など)とは異なり、複数の要素が相互に影響し合う構造を持っています。これは、いわゆる「直交因子」(互いに独立した分類)ではなく、「斜交因子」(一部が重なり合う分類)を考慮した設計になっているためです。そのため、質問の中には「どちらも当てはまる」「どちらもピンとこない」と感じるものがあるかもしれません。これは理論上の特性であり、無理にどちらかを選ぶ前提ではありません。迷ったときは、「どちらでもない」を選んでください。この診断は、厳密な統計モデルに基づいた評価を目的としたものではなく、個々の特性の組み合わせを探るためのものです。一般的な性格分類とは異なる視点を楽しんでいただければと思います。
結果の解説
診断テストの結果の詳細な解説はこちらをご覧下さい。
クアドラ
関連記事「クアドラとは」
アルファ・クアドラ
アルファ・クアドラは、ユーモアや創造的な会話を楽しむ、明るく居心地の良いグループを好みます。議論や交流は深刻になりすぎず、ジョークや軽妙な話題を交えながら進みます。形式ばった礼儀や抑圧的な雰囲気を嫌い、オープンで自然体な関係性を重視します。誰とでも気軽に打ち解けますが、距離を取るのもあっさりしています。情報の共有や分析では、日常の中のユニークな発見や観察に興味を持ち、それを皆で共有して盛り上がる傾向があります。重苦しい感情やドラマを避け、楽しさを中心とした「精神的な調和」を大切にします。恋愛でも遊び心や日常の楽しみを共有することが関係維持の鍵となり、親密さは快適さと笑いによって育まれます。
ベータ・クアドラ
ベータ・クアドラは、大規模で秩序あるグループを好み、皆が参加できる雰囲気づくりに力を入れます。内輪ネタで排除するよりも、派手で一般的なジョークで場を盛り上げる傾向があり、会話は早口で感情的です。個人的な話題を公にすることは裏切りと見なし、場の統一感を大切にします。恋愛では、激しい感情表現と官能的な交流を重視し、19世紀的ロマン主義のような苦悩や劇的要素を求めるため、平穏で淡白な関係には物足りなさを感じがちです。
ガンマ・クアドラ
ガンマ・クアドラは、小規模で落ち着いた集まりを好み、大笑いや感情表現は控えめで皮肉やウィットを楽しみます。真面目な話題にも率直で、恋愛や仕事、投資の見通しなど現実的な話を好みます。大人数の賑やかな場は苦手で、近くの少人数と深い話をするか黙って過ごすことが多いです。恋愛では儀式的な求愛には重きを置かず、最初から関係の見通しを立てる傾向があります。始まると肉体的で激しさのあるやり取りやパワーゲーム的なコミュニケーションが特徴です。
デルタ・クアドラ
デルタ・クアドラは、グループ内で生産的な活動や各自の興味を共有することに価値を置きます。笑い方は控えめで短めですが頻度は多く、ウィットを交えて歓迎的な空気を作ろうとします。ただ、統一された目的や一体感にはこだわらず、個々が自分の興味を追求しつつ、必要なら他人に便宜を図る程度で良いと考えます。そのためグループは分裂しやすく、最終的には同じ興味や感情を持つ小集団が残ることが多いです。恋愛では、強い感情表現やロマンチックな演出は少なく、今現在の快適さや実用性を重視します。活動やアイデアを共有できる相手との関係に心地よさを感じ、将来像よりも現在の楽しさを優先します。
認知スタイル
関連記事「認知スタイルまとめ」
因果的・決定論的
因果的・決定論的認知なスタイルは、物事を原因と結果の連鎖で捉え、論理的・体系的に分析する思考法です。形式論理や決定論的思考に基づき、現象を抽象的な原理に還元して説明することに長けています。問題解決では因果関係を重視し、計画的に行動します。科学・技術分野に適性が高く、説得力ある分析を可能にしますが、感情や予測不能な要素を軽視し、柔軟性に欠ける傾向があります。ストレス時には論理破綻への不安を抱きやすくなります。
弁証法的・アルゴリズム的
弁証法的・アルゴリズム的な認知スタイルは、対立する視点や要素を統合し、柔軟かつ論理的に問題を解決する思考法です。複雑な状況や変化に適応しやすく、創造性や予測力に優れています。直感と論理を組み合わせて動的に対応し、プログラミングや戦略分野に適性があります。一方で、分析過剰や不確実性への弱さが課題となることがあり、批判的思考が行き過ぎると自己消耗や柔軟性の低下を招く可能性もあります。
ホログラフィック・パノラマ的
ホログラフィック・パノラマ的な認知スタイルは、物事を多角的かつ全体的に把握し、視点を自在に切り替えながら理解を深める思考方法です。全体像をすばやく捉え、複雑な情報を整理・統合する力に優れ、創造的な解決策の提示が可能です。一方で、細部への注意が薄れたり、視点の広がりがかえって他人に伝わりにくくなる課題もあります。柔軟で冷静な判断力を持ち、芸術や戦略など多面的理解が求められる分野で力を発揮します。
ヴォーティカル・シナジェティクス的
ヴォーティカル・シナジェティクス的な認知スタイルは、自然のしくみのように、物事が自然にまとまっていく流れを活かしながら、試行錯誤を重ねて目標に近づいていく考え方です。直感と実際の経験を重視し、失敗も前向きにとらえて挑戦を続けます。創造力があり、問題を柔軟に解決するのが得意ですが、試すことに夢中になりすぎて迷走したり、疲れてしまうこともあります。うまく進めるには、試す姿勢と落ち着いた判断のバランスが大切です。
二分法
内向・外向
内向:精神的エネルギーが内面に向かいやすく、自分の思考や感情に集中する傾向があります。一人の時間を通じてエネルギーを回復し、外部との関わりでは必要以上に主導しようとはしません。社交的であることもありますが、相手に主導権を委ねる形で交流を築くのを好みます。内向は「引っ込み思案」とは限らず、むしろ静かに自分の世界を深める姿勢として理解されます。
外向:エネルギーが外界に向かいやすく、自分の外にある事象や他者に注意を向ける傾向があります。他人との関わりから活力を得ることが多く、場の流れを自分から作り出そうとします。社会的に目立つとは限りませんが、他者との相互作用では自分が主導権を握ることを好みます。多くの場合、外的な環境に適応しやすく、行動的で人間関係を築くことに積極的です。
感覚・直観
感覚:目に見える具体的な物事や現実の詳細に注目する知覚のスタイルを指します。今ここで起きていること、身体的な快・不快、物の状態や変化に敏感です。現実志向で、理論より実践を重視し、物事を五感を通じて捉えようとします。外界の動きに反応するSe(外向感覚)と、体内の感覚や環境の変化に繊細なSi(内向感覚)という2つの形式があります。
直観:目に見えない可能性やつながり、変化の兆しなどを捉える知覚のスタイルです。現実の細部よりも全体像や背景にある意味、将来の展開に関心を持ちます。抽象的で理論的な思考を好み、空間よりも時間や概念を重視します。外的な可能性を探るNe(外向直観)と、時間的流れや内的イメージに焦点を当てるNi(内向直観)の2つの形式があります。
倫理・論理
倫理:人間関係や感情、主観的な態度といった、人間的・情緒的な事柄に注意を向ける心理機能のことです。感情の流れや他者の気持ちを読み取ることに長けており、良し悪しといった倫理的価値判断を重視します。説得や人間関係の調整が得意な一方で、論理的な仕組みや手順の扱いには弱さが出ることがあります。Fi(内向倫理)とFe(外向倫理)の2種類があります。
論理:客観的な事実、システム、手続きなど、人間以外の構造的・測定可能な内容に注目する心理機能です。正誤や因果関係を見極めることを重視し、思考や判断を合理性に基づいて行います。議論を好む傾向があり、倫理的な配慮に欠けると対人関係に課題を抱えることもあります。Ti(内向論理)とTe(外向論理)の2種類があり、全タイプの半数はこの論理機能を中核に持っています。
合理・非合理
合理:計画を立てて順序立てて物事を考える傾向を指します。決断を早く下し、途中で変更することを好まず、始めたことを最後までやり遂げようとします。動作や態度はやや堅く、リーダーシップも権威的になりがちです。ただし、これは「生得的な思考プロセス」の特徴であり、一般的な「論理的」「賢明」といった意味とは無関係です。
非合理:柔軟に対応しながら物事を進める傾向を指します。決断は即断よりも様子見を好み、状況に応じて判断を変えることが多く、新しいことへの移行も速いです。動きは自然体で、民主的なスタイルをとることが多く、変化にも比較的強いです。これは感覚や直観といった「知覚」から判断を導く思考スタイルを示しており、通俗的な「非論理的」とは全く異なる意味合いです。
中心・周辺
中心(別名:果敢):「動員状態」が自然なあり方で、必要になる前から無意識に準備し、タスク完了後もすぐには気が抜けません。一気に取り組む「キャンペーン型」の働き方を好み、報酬を重視します。作業全体に集中し、実行段階を明確に意識しています。快適さより成果を優先し、自分の決断を自らの意思と捉える傾向があります。決断や成果に注目し、「結果」や「お金」についてよく語ります。全てのベータクアドラとガンマクアドラはこちらに分類されます。
周辺(別名:賢明):リラックスした「弛緩状態」が自然なあり方で、必要なときだけ集中して動員されます。作業は小さく分けて進め、その間に頻繁に休息を取ります。準備や計画段階を重視し、実行はあまり意識に上りません。職場では快適さや利便性を重視し、成果のために労働条件を犠牲にしません。決断のプロセスを重んじつつ、行動開始の瞬間はあまり記憶に残らず、状況に促されて動く傾向があります。全てのアルファクアドラとデルタクアドラはこちらに分類されます。
情緒・構成
情緒:人との関わりの中で感情の流れや雰囲気に強く影響され、それを整えたり保ったりしようとする傾向です。会話では内容よりも感情の状態そのものに意識が向き、雰囲気づくりを活動とみなします。新しい感情体験を好み、繰り返しよりも変化を重視します。感情的な話題から切り離されることは苦にしませんが、具体的な要求や検討を迫られる状況には弱く、現実的な負担を避けようとする傾向があります。
構成:人との関わりにおいて感情的な要素をできるだけ避け、実務的・議論的なやり取りを好みます。感情を「再体験」することを重視し、自分の内面と響き合うような特定の本や場所、音楽などを繰り返し利用して心の状態を保とうとします。感情に入り込むと切り替えが苦手で長く影響を受けるため、不快な感情や刺激を事前に避けようとします。相手の感情よりも、自分の感情の管理の方に敏感です。
主観・客観
主観:感情的な雰囲気に敏感で、人と自然に打ち解けることが得意です。個人の意見や立場を重視し、「真理」は人それぞれ異なると考えます。行動の是非は自分の内的基準で判断し、他者にもそれぞれ異なる基準があると理解しています。共通の枠組みではなく、自分なりの概念を示し、「こう見るべき」という視点の共有を好みます。形式的な挨拶や肩書にはあまり意味を見出さず、その場その場の関係性を柔軟に築いていきます。全てのアルファクアドラとベータクアドラはこちらに分類されます。
客観:形式的な関係のステップや儀式を重視し、感情的な雰囲気にはあまり敏感ではありません。「真理」や「正しさ」は個人の主観を超えた客観的基準に基づくと考えます。行動の評価も「一般的に正しい方法」との比較で行います。他者と接する際は、相手の名前や立場などを重視し、きちんとした紹介を必要とします。意見が対立した場合は、「正しい定義」や「共通理解の有無」に注目し、方法や用語の検証ではなく、正解の提示を重視します。全てのガンマクアドラとデルタクアドラはこちらに分類されます。
戦略・戦術
戦略:「目標(ゴール)」を中心に物事を捉え、どのように到達するかは柔軟に考えます。過去の経験も、結果に結びついた「決定的瞬間」に着目して評価します。自分の行動が目標に近づいているかを基準に判断し、目標がないと不安や空虚を感じます。目標設定に強い意識を持ち、一度立てた目標を手放すことに抵抗を覚える傾向があります。語彙には「目標」「目的」といった言葉が多く見られ、それらを明確に言語化する力があります。
戦術:「今この瞬間の状況」や「実際の行動や出来事」に強く意識を向け、最終的な目標にはあまり重きを置きません。道筋そのものが重要であり、目標は状況に応じて変わり得る流動的なものです。過去の選択肢や可能性を等価に捉える傾向があり、複数のルートを同時に意識します。長期的な計画には向かず、「方向性」「方法」「課題」などの語彙を用いて、自らの行動を語ることが多いです。目標達成後には空虚感を抱くこともあります。
利益・資源
利益:関心や追求する対象こそがパーソナルスペースであり、自分の核心部分です。その関心を追求するためなら、リソース(時間や体力)を調整・交換・犠牲にすることも厭いません。興味がある限り粘り強く取り組み、簡単には手放さず、未達成でも保留して追求の機会を待ちます。自分の利益が脅かされることに敏感で強く反発しますが、リソース自体の喪失には比較的寛容です。利益は不可侵、リソースは操作可能という価値観を持ちます。
資源:自分の「リソース(時間・体力・能力など)」をパーソナルスペースとして捉え、他者に侵害されることに非常に敏感です。興味・関心は調整可能で、リソースがなければ自然と関心も薄れます。他者との関わりは柔軟ですが、自分が何に取り組むかはリソースの範囲内に限定します。無理なことは最初から避け、興味を持っても実現不可能ならすぐ切り捨てます。リソースは不可侵、関心は操作可能という価値観を持ちます。
動的・静的
動的:物事を連続した流れとして捉え、変化やプロセスに注目します。物語や出来事の描写では「今まさに起こっていること」や移り変わる過程が重視され、登場人物も場面ごとに主役が入れ替わるように描かれます。抽象化せず具体的に語る傾向があり、自身がその中に没入しているような感覚を伴います。
静的:現実を区切られた場面や状態の集合として捉えます。出来事を抽象化して一般的に語る傾向があり、物語では一定の状態や主人公が維持されやすく、連続的な変化よりも各場面の特徴や状態に焦点が当たります。変化は連続ではなく、飛び飛びの切り替わりとして把握されます。
貴族・民主
貴族主義:人を認識したり関係を築いたりする際に、その人が属するグループや社会的カテゴリー(職業、出身地、階層など)を重視します。「私たち」と「彼ら」といった枠組みで世界を捉える傾向が強く、個人は集団の代表として見られがちです。話し方にも「典型的な〜」「我々の〜」といった表現が多く使われます。個人の評価は、その人が属する枠組みによって強く影響されます。全てのベータクアドラとデルタクアドラはこちらに分類されます。
民主主義:個人の特徴や資質を重視して人を理解しようとします。相手の所属グループやカテゴリーには関心が薄く、ステレオタイプを避ける傾向があります。「私は私」として自分を定義し、他者も独立した存在として扱います。対人関係では「その人自身がどうか」が最も大切であり、関係性も一対一の親密さを基準に築かれます。カテゴライズに抵抗感があり、集団よりも個人を優先する姿勢です。全てのアルファクアドラとガンマクアドラはこちらに分類されます。
宣言・質問
宣言:モノローグ的な話し方を好み、話し中に質問されることを嫌います。話は断定的で自信に満ち、相手が話し終わるまで待ってから質問や反論をします。会話は交代制のように進み、質問をしても明確な答えを求めます。話の流れが遮られると混乱することがあるため、自分のペースを大切にします。対話よりも一方的に語る形式を好み、会話の主導権を取る傾向があります。
質問:対話的で流動的な会話を好み、会話中に質問を挟んだり、質問に質問で返したりする傾向があります。話し方は断定的でなく、問いかけを通して会話を展開します。話の途中に質問されてもすぐに答え、また元の話に戻る柔軟性があります。仮にモノローグであっても、内的対話のようになりがちで、常に相手とのやりとりを求めます。会話は構造よりも流れを重視し、即興的に展開します。
先見・臨機
先見:問題を解決する際に、過去の経験や蓄積された知識を広く参照し、事前に準備された方法を使って対応します。新しい状況に対しても「過去に似たことがあった」として、再利用できる情報を活用します。行動には根拠や背景があり、他人に説明する際には、準備・状況・意図などを丁寧に語る傾向があります。予想や予期は「具体的に何が起きるか」を例を挙げて説明しようとします。
臨機応変:今目の前にある状況や情報に基づいて、その場に最も合ったやり方を見つけ出すことを好みます。準備よりも対応力を重視し、過去の経験を明示的に引き合いに出すことは少なく、柔軟な判断で行動します。考えや行動の理由を詳細に語ることはあまりなく、結果的にうまくやれるという感覚があります。会話では「全部を予測するのは無理」「必要そうなことだけをやる」といった姿勢が見られます。
結果・プロセス
結果:自分をプロセスの外側に置き、プロセスを管理・評価する視点を重視します。複数の事柄を同時に扱うのが得意で、各プロセスの開始点や終了点に注目し、成果や完了状況を確認することで安心感を得ます。進行中の物事を定期的に見積もり、ゴールや結果が見えるように設計する傾向があります。プロセスの途中経過よりも、最終的なアウトカムへの到達が重要視されるのが特徴です。
プロセス:物事を進行中のプロセスとして捉え、その中に没入します。始点や終点よりも、プロセスそのものの流れや一体感を重視し、一度始めたら中断せずに続けたい傾向があります。複数の物事を同時に進めるのは苦手で、一つひとつを順にこなす方が自然です。過去に中断したプロセスを再開することは困難で、再開には新しいエネルギーや覚悟が必要となります。
否定・肯定
否定主義:物事の欠点や不足に着目し、失敗や損失を避けることを重視する姿勢です。「何がうまくいかなかったか」「何をしてはいけないか」といった視点から状況を捉えます。肯定的な展望よりも、否定的な結果を避けたことに価値を見出します。表現も否定形が多く、「~しないで」「~ではない」と伝える傾向があり、楽観的すぎる態度には警戒や不信感を抱きやすいです。危機回避型で、準備と警告に重点を置く傾向があります。
肯定主義:物事の良い面や可能性に注目し、成功や前進を目指す姿勢です。「何ができるか」「何があるか」という肯定的な視点から物事を捉え、前向きな表現を好みます。失敗よりも成果に関心を向け、他者との関わりにおいても信頼や成長を重視します。否定的な経験ですら意味あるものとして受け止めようとし、会話では「~すればいい」「~がある」といったポジティブな言い回しが多くなります。明るく建設的なコミュニケーションを志向します。
情報要素
外向的論理(Te)
外向的論理(Te):外で起こる事実や動きを客観的に整理する機能です。例えばイベントや作業、機械の動きを見て「何が」「どこで」「どうやって」行われているかを理解します。Teタイプの人は、こうした観察可能な情報から論理的に意味を見出し、どれだけ実用的か、目的達成に役立つかを分析します。評価基準は「目的をどれだけ効果的に果たしているか」であり、無駄なく成果を出すことを重視する傾向があります。
内向的論理(Ti)
内向的論理(Ti):Tiは、物事を筋道立てて理解し、体系化・分類して整理する能力と関わります。常識や権威を無条件に信じず、自分の論理で納得できるかを基準に判断します。正確性、美的整合、対称性などを重視し、曖昧さや冗長な説明を嫌います。世間の多数派よりも、自分の中で筋が通るかを重視し、「とにかく役立てばよい」という考えには浅さを感じる傾向があります。
外向的倫理(Fe)
外向的倫理(Fe):人の感情や場の雰囲気を敏感に感じ取り、それを周囲に伝えて盛り上げる力です。一体感や協力的な空気を大切にし、感情をこめて話したり表現を強調して、人を引き込みます。細かい気遣いよりも自然な心地よさを重視し、激しい口論後も恨みを残しにくい傾向があります。また、黙るよりも率直に感情を表す方が関係維持に良いと考えます。
内向的倫理(Fi)
内向的倫理(Fi):人と人とのあいだにある「心の距離感」や「関係の質」を繊細に感じ取る感覚です。親密さ・礼儀・思いやり・違和感といった人間関係の機微に強く反応し、自分や身近な人との感情的な調和を重視します。Fiを重んじる人は、深い絆や誠実なつながりを大切にし、他者の感情を敏感に察知します。また、感情を語る際は「自分の内面からの実感」に基づいて判断する傾向があり、集団全体よりも個人の誠実さや真心を重視します。
外向的感覚(Se)
外向的感覚(Se):外部世界に対して直接的に影響を与える力や存在感、権力に関わる情報要素です。領域を守る・奪う、主導権を握る、相手に圧力をかけるなど、現実における力の動きに敏感です。争いや欲望、行動力を通じて結果を得ようとし、場の主導を取ることに長けています。目的のために即行動し、他者を動かす力に価値を置きます。対照的に、穏やかな感覚や内面の快適さよりも、外部への影響力を優先します。
内向的感覚(Si)
内向的感覚(Si):自分の身体感覚や身の回りの快・不快、居心地のよさ、美しさなどに細やかに気づく力です。空間や物の関係、体感温度、感触などの微細な変化に敏感で、「今ここ」の体験を落ち着いて味わいます。何かを得るために動くよりも、自分が心地よく過ごせるかどうかに意識が向き、争いを避けて穏やかに調和を保とうとします。目標も他人の期待ではなく、自分の内から湧く自然な願いに基づいて決める傾向があります。
外向的直観(Ne)
外向的直観(Ne):「まだ現実になっていない可能性」に目を向ける力です。未来の選択肢やチャンス、隠れた才能などを素早く察知し、ひらめきやアイデアを次々に生み出します。試行錯誤を恐れず、複数の道を模索する柔軟さがあります。他人の個性や考え方の違いにも寛容で、対立する意見をつなぐ調整力も備えます。突飛なアイデアや面白い発想を好み、ユニークな切り口で世界を語る傾向があります。抽象的な意味や本質を探るのが得意です。
内向的直観(Ni)
内向的直観(Ni):Niは「時間の流れ」に敏感で、物事の変化や展開の方向性、未来の可能性を直観的に読み取る能力です。過去・現在・未来のつながりを把握し、「今ここ」よりも「これからどうなるか」に意識が向かいます。何気ない出来事の背後にある意味や流れを探ろうとし、心理的なイメージや未来のビジョンを重視します。遊びにも目的や意味を求めやすく、目標や成長の道筋を想像して行動する傾向があります。現実より内面の時間感覚が重要です。